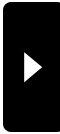2021年07月02日
熊野の里、池田のまちに文化が薫る、伝統が舞う
池田の観光といえば、やはり磐田市を代表する春の観光スポットでもある「熊野の長藤」といえるでしょう。それは、800年前に遡る歴史と、美しくも悲しい物語の舞台があるからです。
平家物語にも登場する熊野は、旧豊田町がかつての一部であった池田の荘の庄司の娘でした。時の権力者「平宗盛」に寵愛された熊野は才媛の誉れが高く、その優しい心根は世阿弥作と伝えられる謡曲「熊野」として今日まで語り継がれています。
旧豊田町では、熊野御前のように多くの人に愛さる街を目指し、熊野御前没後800年を機に「熊野800年祭」の様々な事業に取り組みました。その事業の一つとして「熊野伝統芸能館」がオープンしました。 行興寺境内の「熊野の長藤」から連なる藤棚を借景として屋外型の能楽堂は、見る人を深い幽玄の世界にいざなうことでしょう。連綿と受け継がれてきた文化を、この舞台がさらに広く豊かに次世代へと伝えて行きますよう希望が込められています。
能楽堂のこけら落とし公演に、観世流二十六世家元「観世清和師」による能公演が上演されました。


▲観世流の監修による熊野伝統芸能館
屋外型の能楽堂は全国でも希少な存在です。毎年5月下旬に「磐田能」が上演されています。

▲行興寺境内の樹齢800年とも伝えられる藤は、国の天然記念物に指定されています。

▲毎年5月3日、行興寺で熊野御前供養祭が行われています。
熊野御前って、どんな人?
「熊野の長藤」は花の名所としても有名ですが、「平家物語」に登場する「熊野御前」に関わる歴史背景や長藤の由来をご紹介します。
熊野が生きた時代は、今から800年ほど前の平安末期にさかのぼります。池田の宿に美しくて優しい女性が住んでいました。池田荘の庄司藤原重徳の娘で、和歌山県の熊野権現に祈願して生まれたことから「熊野(ゆや)」と名付けられました。熊野は才色とも優れ和歌の道に通じ、親孝行でもあり当時は女性の手本とされたそうです。
ある時、遠江国の国司(地方長官)として赴任してきた平宗盛(平清盛の三男)に見染められ、寵愛を受けることになります。そして、国司の任を終えた時、宗盛は熊野を京の都に連れて帰ったのです。熊野は「熊野御前」として宗盛に仕え優雅な生活を送ることになりました。しばらくして郷里の母が病に倒れたとの知らせが届きます。親思いの熊野は、すぐにでも池田に帰りたいと宗盛に訴えますが、なかなか許しが出ません。そんなある日、熊野は清水寺の花見の宴で、得意の和歌を一首詠みました。「いかにせん 都の春も惜しけれど なれし東(あずま)の花や散るらん」と今の心情を宗盛に捧げました。華やかな都の春は名残惜しいけれど、住み慣れた東国(池田)では、愛する母の命が散ろうとしているという歌を詠んだのです。この歌に宗盛は心が動かされ、ついに熊野の帰郷を許したのです。
熊野が池田に帰って間もない頃、源氏と平氏の最終決戦である壇ノ浦の戦いで平氏は滅亡。宗盛も命を落とします。その後、両親も亡くした熊野は尼となり、現在の行興寺の場所に念仏道場を建てました。そして道場の境内に藤の木を植え、それが「熊野の長藤」のもとになったと伝えられています。
この物語は能の名曲「熊野」に描かれ、その歴史背景をもとに隣接する公園内には、観世流監修の立派な能舞台が設けられました。行興寺の藤は「熊野の長藤」と親しまれ、国・県の天然記念物に指定されています。熊野御前の墓は、母の墓とともに行興寺にあり、今も香の煙が絶えることがありません。毎年、熊野の命日の5月3日に熊野御前供養祭が行われます。
平家物語にも登場する熊野は、旧豊田町がかつての一部であった池田の荘の庄司の娘でした。時の権力者「平宗盛」に寵愛された熊野は才媛の誉れが高く、その優しい心根は世阿弥作と伝えられる謡曲「熊野」として今日まで語り継がれています。
旧豊田町では、熊野御前のように多くの人に愛さる街を目指し、熊野御前没後800年を機に「熊野800年祭」の様々な事業に取り組みました。その事業の一つとして「熊野伝統芸能館」がオープンしました。 行興寺境内の「熊野の長藤」から連なる藤棚を借景として屋外型の能楽堂は、見る人を深い幽玄の世界にいざなうことでしょう。連綿と受け継がれてきた文化を、この舞台がさらに広く豊かに次世代へと伝えて行きますよう希望が込められています。
能楽堂のこけら落とし公演に、観世流二十六世家元「観世清和師」による能公演が上演されました。

▲観世流の監修による熊野伝統芸能館
屋外型の能楽堂は全国でも希少な存在です。毎年5月下旬に「磐田能」が上演されています。

▲行興寺境内の樹齢800年とも伝えられる藤は、国の天然記念物に指定されています。

▲毎年5月3日、行興寺で熊野御前供養祭が行われています。
熊野御前って、どんな人?
「熊野の長藤」は花の名所としても有名ですが、「平家物語」に登場する「熊野御前」に関わる歴史背景や長藤の由来をご紹介します。
熊野が生きた時代は、今から800年ほど前の平安末期にさかのぼります。池田の宿に美しくて優しい女性が住んでいました。池田荘の庄司藤原重徳の娘で、和歌山県の熊野権現に祈願して生まれたことから「熊野(ゆや)」と名付けられました。熊野は才色とも優れ和歌の道に通じ、親孝行でもあり当時は女性の手本とされたそうです。
ある時、遠江国の国司(地方長官)として赴任してきた平宗盛(平清盛の三男)に見染められ、寵愛を受けることになります。そして、国司の任を終えた時、宗盛は熊野を京の都に連れて帰ったのです。熊野は「熊野御前」として宗盛に仕え優雅な生活を送ることになりました。しばらくして郷里の母が病に倒れたとの知らせが届きます。親思いの熊野は、すぐにでも池田に帰りたいと宗盛に訴えますが、なかなか許しが出ません。そんなある日、熊野は清水寺の花見の宴で、得意の和歌を一首詠みました。「いかにせん 都の春も惜しけれど なれし東(あずま)の花や散るらん」と今の心情を宗盛に捧げました。華やかな都の春は名残惜しいけれど、住み慣れた東国(池田)では、愛する母の命が散ろうとしているという歌を詠んだのです。この歌に宗盛は心が動かされ、ついに熊野の帰郷を許したのです。
熊野が池田に帰って間もない頃、源氏と平氏の最終決戦である壇ノ浦の戦いで平氏は滅亡。宗盛も命を落とします。その後、両親も亡くした熊野は尼となり、現在の行興寺の場所に念仏道場を建てました。そして道場の境内に藤の木を植え、それが「熊野の長藤」のもとになったと伝えられています。
この物語は能の名曲「熊野」に描かれ、その歴史背景をもとに隣接する公園内には、観世流監修の立派な能舞台が設けられました。行興寺の藤は「熊野の長藤」と親しまれ、国・県の天然記念物に指定されています。熊野御前の墓は、母の墓とともに行興寺にあり、今も香の煙が絶えることがありません。毎年、熊野の命日の5月3日に熊野御前供養祭が行われます。
Posted by 池田まちづくり協議会 at 18:07│Comments(0)│池田の観光